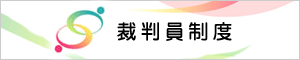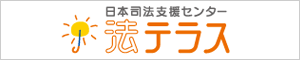![]() 弁護士 今田 健太郎
弁護士 今田 健太郎
2016年06月13日(月)
市民レガッタに参加して
弁護士の今田健太郎です。
恒例の広島市民レガッタに参加しました。私は、これで8年連続出場ということになります。ど素人である私がレガッタを漕ぐというのは、泳げない子どもを、いきなりプールに放り込むようなものです。それでも何とか指導を受けながら、他の素人のクルーと協力してゴールを目指します。毎回ハプニングがありますが、バーベキューなどを楽しみながら、皆さん、この風物詩を楽しんでいます。
私たちのチームは、「広島弁護士会災害対策委員会」というチーム名で出場しているのですが、これは、広島市民の方々に、弁護士が災害時には支援を行いますという、広報を兼ねているものです。
成績は、うーむ。災害があったときに、レガッタで駆けつけられるほどの力量はなさそうですが、皆から心意気だけは伝わってきます。
川の街、広島に育って、太田川には愛着もありますが、まさか弁護士になり、この川をレガッタでのぼっていく、ということなど、考えてもみませんでした。この歴史ある、広島市民レガッタ、そこには、川の街広島を象徴するような、平和的な風景があります。
勝敗もこだわりたいですが、そこに集まる市民の方々と交流し、一体感を共有できる、そんな市民レガッタに、これからも体力の続く限り、災害対策委員会として参加していきたいと思います。