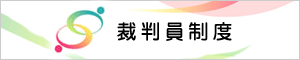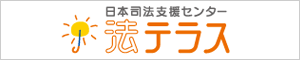![]() 事務局 広島事務所
事務局 広島事務所
2015年01月30日(金)
制服
この度、弁護士法人あすかに念願の制服ができました。
今まで、事務局は私服で仕事をしていたため、少し新鮮な気持ちです。
個人によって、リボンとスカーフ、Aラインスカートとタイトスカート、ジャケットとベストなど小さな違いがあり、個々の好みが反映されているように感じて、個人的には見ているだけでウキウキします。
身も心もキリッとして、これまで以上にお仕事を頑張らなければという気持ちでいっぱいです。
![]() 弁護士 中岡 正薫
弁護士 中岡 正薫
2015年01月27日(火)
一年の計
弁護士の中岡です。
新年を迎えてはや1月が経とうとしていますが、みなさん今年の目標や計画は立てられていますか。
『一年の計は元旦にあり』、何事も始めに目標や計画を立てることが肝心であり、意義ある充実した1年間を過ごすためには大切なことです。
しかしながら、己のこととして振り返ってみると、忙しい日常の生活に追われた結果、年初に立てた目標達成への情熱が春先には薄れ、夏頃には達成を諦め、年末には何が目標であったかさえも忘れてしまう1年を過ごしてしまうことが多かったように思います。
そこで、今年は敢えてブログに公開し、記録に残しておくことで(強制的にでも)目標達成することにしました。
【2015年の目標】
①トライアスロンに出場し、完走すること
②ウルトラマラソンに出場し、完走すること
③本100冊読破
①②は、言わずもがな私の趣味であるマラソンを更に進化させた目標です。トライアスロンの完走者は「アイアンマン」と呼ばれるそうですので、ついでにウルトラマラソンも完走して、ウルトラアイアン弁護士という名誉?ある称号を手に入れようと思います。
③はジャンル問わず、出来ればこれまで全く興味を持ったことのなかった世界の本を読んでみたいです。ちなみに漫画は含みません(含めてしまうと既に目標達成になってしまうので)。
12月にこのブログを見て猛省することのない1年を過ごしたいものです。